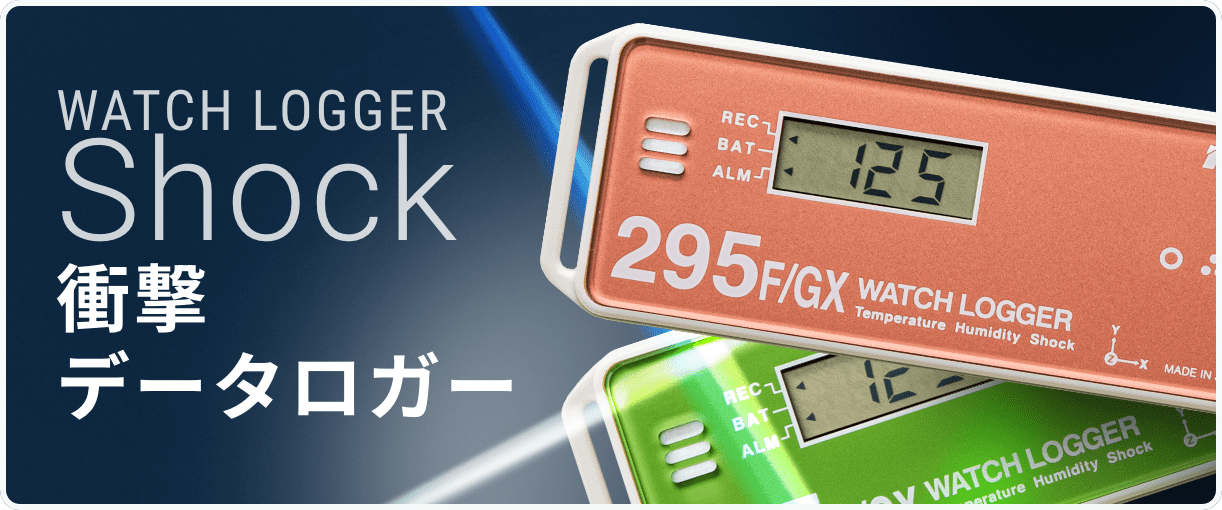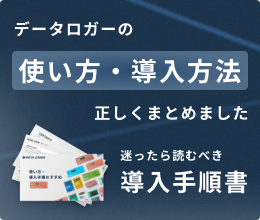物流アウトソーシングとは?メリット・デメリットや導入手順を解説
物流アウトソーシングとは、自社の物流業務を専門業者に外部委託することです。物流の品質向上や効率化、コスト削減などのメリットがあります。
一方、物流アウトソーシングにはデメリットや注意点もあるため、「物流アウトソーシングについてもっと知ってから導入を検討したい」といった担当者の方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、物流アウトソーシングとは何か、対応業務やメリット・デメリットなどについて解説します。物流アウトソーシングを導入する際の手順も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
物流アウトソーシングとは
物流アウトソーシングとは、企業が自社で行っていた物流業務を外部の専門業者に委託することです。物流業務には、商品の入荷・保管・出荷・配送・在庫管理などが含まれ、これらの業務を自社内で完結させるには多くの人員・スペース・設備が必要になります。専門性を持つ外部企業に委託することで、自社のリソースをコア業務に集中可能です。
近年では、EC市場の拡大や消費者ニーズの多様化により、物流の複雑性が増しています。これに対応するため、多くの企業が物流の外部委託に注目し、導入を進めています。とくに、受注処理や在庫管理、配送業務などの煩雑な作業を外部化することで、業務の効率化と品質向上の両立を実現できる点が大きなメリットです。
関連記事
食品物流のアウトソーシングとは?メリットや業者の選び方を解説
医薬品物流のアウトソーシングとは?メリットや注意点を解説
物流アウトソーシングの対応業務
物流アウトソーシングを利用すると委託できる業務は、主に以下の7つです。
- 入荷・入庫
- 検品
- 在庫管理・棚卸
- 帳票発行
- ピッキング・梱包
- 出荷
- 返品処理
それぞれ詳しくチェックしてみましょう。
入荷・入庫
入荷・入庫は、物流倉庫に商品が到着した際の荷受け作業です。外部業者は、商品の到着を確認し、伝票との照合や破損の有無をチェックしたうえで、指定された保管場所に商品を入庫します。後続の在庫管理や出荷の効率に直結する重要な作業の1つです。
検品
入庫後に行う検品作業は、商品の数量・型番・外観・品質などが発注内容と一致しているかを確認する重要な工程です。物流アウトソーシング業者は、バーコードリーダーやRFIDシステムを活用して効率的かつ精度の高い検品作業を行います。不良品が発見された場合には、返品処理や報告書の作成も業者が代行するケースが一般的です。
在庫管理・棚卸
在庫管理・棚卸は、在庫の数量や保管状況をリアルタイムで把握し、過不足のない在庫を維持するための管理業務です。物流業者はWMS(倉庫管理システム)などを活用し、在庫データを常に最新の状態に保つとともに、定期的な棚卸作業も代行します。
帳票発行
出荷伝票や納品書、請求書などの各種帳票を正確に作成・発行する作業も、物流業務に含まれます。物流業者は、基幹システムと連携して帳票の自動出力に対応しているケースが多く、手作業によるミスを防ぎながら業務のスピードを向上させています。
ピッキング・梱包
注文内容に応じて必要な商品を棚から取り出すピッキング作業、商品を破損なく届けるための丁寧な梱包作業も対応業務の一部です。業者は、作業効率を上げるためにゾーンピッキングやウェーブピッキングなどの方式を採用し、複数注文を同時処理する体制を構築しているケースもあります。
出荷
出荷は、顧客への商品発送に関する一連の業務です。運送業者への引き渡し、送り状の発行、配送状況の追跡などを一括して対応します。発送ミスや遅延が発生しないように、出荷前の検品体制も整備されており、出荷後の問い合わせ対応まで一任できる業者もあります。
返品処理
返品された商品の受け入れ・状態確認・再入庫または廃棄などの処理も、外部業者に委託可能です。返品理由の分析や報告書の作成、顧客対応まで対応する業者もあり、返品による手間を大幅に軽減できます。
物流アウトソーシングの種類
物流アウトソーシングと一口に言っても、提供形態にはさまざまな種類があります。企業のニーズや物流体制に応じて、最適なサービスを選定することが重要です。
第三者物流(3PL)
3PL(Third Party Logistics)とは、企業が自社の物流機能全体または一部を、外部の物流専門会社に包括的に委託する形態です。物流業務の計画立案から実施、管理に至るまでをトータルでサポートするため、物流部門そのものをアウトソーシングできます。
3PLの利点は、物流コストの可視化や削減が可能になる点や業務の効率化、サービスレベルの向上です。物流業者の専門的な知見や最新のシステムを活用することで、常に最適な物流体制を維持できます。
第四者物流(4PL)
4PL(Fourth Party Logistics)は、3PLをさらに進化させた形態で、物流業務の設計・戦略立案・プロジェクト管理といった「上流工程」を担うのが特徴です。4PLは複数の3PL業者を統括・管理し、全体最適の物流戦略を構築します。
4PLは物流業務のアウトソースだけでなく、全体の統制と最適化を図る役割を担います。多拠点展開している企業や、グローバルなサプライチェーンを構築している企業に適したサービスです。
定額系物流サービス
定額系物流サービスとは、一定の荷量や業務内容に対して、定額でサービスを提供するアウトソーシング形態です。月額固定の料金体系が多く、コストの見通しが立てやすいのがメリットです。
ただし、荷量が大きく変動する企業にとっては、定額契約がコスト的に不利になることもあります。自社の出荷量や繁閑の差を踏まえたうえで、契約内容の慎重な検討が必要です。
カスタム系物流サービス
カスタム系物流サービスは、企業ごとに異なる物流課題やオペレーションに応じて、柔軟にカスタマイズされた物流サービスを提供する形態です。標準的なパッケージプランでは対応しきれない特殊な工程や業種固有の要望にも対応できます。
たとえば、検品基準が厳しいアパレル業界や、ロット管理が重要な医療・化粧品業界などには、定額系よりもカスタム系が適している傾向があります。業者と綿密に連携し、最適な物流体制を構築することが重要です。
物流アウトソーシングを利用するメリット
物流アウトソーシングを利用するメリットとして、以下の4つを解説します。
- コストの明確化・削減が期待できる
- 繁忙期と閑散期の変化に対応できる
- 業務を効率化できる
- 物流の品質が向上する
コストの明確化・削減が期待できる
物流業務には、倉庫の維持費、作業員の人件費、梱包資材の費用、出荷にかかる配送コスト、さらにはシステム運用やITインフラの維持費など、さまざまなコストが発生します。これらを社内で管理している場合、各費用が部門をまたいで発生していたり、変動費と固定費が混在していたりすることで、全体像が不透明になりやすいのが課題です。
物流アウトソーシングを導入することで、こうしたコスト構造を明確化しやすくなります。委託費用として一元的に計上されるため、部門間のコスト分担を可視化できるほか、業務ごとに明細が分かれているケースでは、作業別のコスト分析も可能です。
さらに、外部業者はスケールメリットを活かして作業効率や単価を最適化しているため、自社で対応するよりも人件費や運送費を抑えられるケースが多くあります。倉庫スペースの共有や配送ルートの統合などにより、物流コストを構造的に引き下げることができる点も、外注の大きな魅力です。
繁忙期と閑散期の変化に対応できる
多くの企業では、年間を通じて注文量や出荷件数に波があります。たとえば、ECサイトにおけるセール期間や年末商戦、季節商材を扱う業種では、一定の時期に業務量が集中する繁忙期が存在します。一方、閑散期には出荷量が極端に減るため、物流リソースが過剰になることもあるでしょう。
物流アウトソーシングを活用すれば、業務量の変動に応じて柔軟に対応できる体制を構築することが可能です。業者は複数の荷主企業を抱えており、リソースを全体最適の観点で配分しているため、一社ごとの荷量増減にも比較的スムーズに対応できます。
とくに中小企業にとっては、必要な時に必要な分だけ物流リソースを活用できる点が大きな利点です。また、人的リソースに限りがある企業では、社内の社員を販促や営業などのコア業務に集中させることができ、生産性向上にもつながります。
業務を効率化できる
物流業務には、受注処理・在庫管理・ピッキング・梱包・出荷といった一連の作業が含まれており、それぞれの工程で正確さとスピードが求められます。これらの業務を自社で一貫して行うには、業務ノウハウの蓄積や最新のシステム導入、教育・訓練などが必要です。
物流アウトソーシング業者は、これらの業務を専門的に運用しており、高い精度と効率を兼ね備えた業務フローを確立しています。ルーティン作業のアウトソーシングによって、自社の従業員が物流以外の業務に注力できるようになり、企業全体の業務効率や生産性も向上するでしょう。
物流の品質が向上する
専門業者に任せることで、納期遵守率や誤出荷率といった物流KPIの改善が期待できます。たとえば、トレーサビリティやバーコード管理の導入により、在庫管理の精度が向上したり、誤配送リスクが低減したりといった効果を期待できるでしょう。
また、物流の専門業者は配送業者との連携もスムーズで、顧客満足度の向上にもつながります。とくにECなど顧客接点が重要な業態において、こうした物流の品質は競争力強化のための重要なポイントです。
物流アウトソーシングを利用するデメリット
物流アウトソーシングを利用するデメリットは、主に以下の4点です。
- 柔軟な対応が困難になるケースがある
- 委託できる業務は業者によって異なる
- 自社に物流のノウハウが蓄積されない
- 責任の所在が曖昧になるリスクがある
各デメリットについて確認しておきましょう。
柔軟な対応が困難になるケースがある
物流業務を外部に委託する場合、ある程度業務フローが固定化されるため、突発的な変更や即時対応が難しくなることがあります。たとえば、新商品の緊急出荷や販促キャンペーンに伴う一時的な作業変更、急な納品先変更など社内であれば即日対応できる内容でも、外部委託先では柔軟に動けない場合がある点には要注意です。
とくに、業務の一部しか共有されていない外部委託先では、事情を十分に把握できず、対応に時間がかかったり、意図しない処理が行われたりするリスクもあります。また、イレギュラー対応には追加料金が発生することもあるでしょう。
業務委託契約時に、どの範囲までの変更対応が可能か、緊急時の連絡ルートや優先順位の取り決めを明確にしておくことが重要です。
委託できる業務は業者によって異なる
すべての業者がすべての物流業務に対応しているわけではないという点にも注意しましょう。業者によっては、特定の工程に特化している場合もあれば、EC特化型やBtoB特化型など、対応できるサービスや対象商材に制限がある場合もあります。
たとえば、温度管理が必要な食品や医薬品の物流には、専用の保冷設備や輸送体制が必要になりますが、これに対応できる業者は限られます。また、アパレル商品であればサイズ・色・タグなどの細かい管理や、店頭納品向けのハンガー吊り対応が求められるため、対応可能な業者の慎重な選定が必要です。
導入前には、業務内容を一覧化し、自社が委託したい作業のすべてを網羅している業者かどうかを細かくチェックすることが不可欠です。また、できる限り業務の可視化・標準化を進めておくことで、業者とのすり合わせがスムーズになります。
自社に物流のノウハウが蓄積されない
物流業務を外部に任せることで、自社の社員が日常的に物流の現場に携わる機会が減少します。これにより、物流に関する知識やノウハウが社内に蓄積されず、業者に依存した体制が長期化する恐れがある点には要注意です。
この課題への対応としては、外部委託をしていても一定の範囲で物流管理を内製化し、定期的に業者からの報告を受けて内容をレビューする仕組みを構築することが有効です。自社内に物流担当者やロジスティクス責任者を配置し、業者とのコミュニケーションを通じて現場感覚を維持することも重要です。
責任の所在が曖昧になるリスクがある
物流アウトソーシングでは、商品の誤出荷・遅延・破損などのトラブルが発生した際に、どの工程でミスが起きたのか、誰が責任を負うのかが不明瞭になりやすいのも注意点です。たとえば、社内での受注処理ミスなのか、倉庫でのピッキングミスなのか、配送中の破損なのかによって、対応方法や補償範囲は大きく異なります。
このようなリスクを回避するためには、業務委託契約書において、各工程の責任範囲やミス発生時の対応ルールを詳細に定めておきましょう。また、日々の業務ログや作業記録をしっかり残し、トレーサビリティを確保する体制を業者と共有しておくことで、問題発生時の迅速な原因特定が可能になります。
物流アウトソーシングを依頼する業者の選び方
物流アウトソーシングを依頼する業者の選び方として、以下の4つのポイントを解説します。
- 自社の物流にマッチしている業者を選ぶ
- 見積もり金額が妥当な業者を選ぶ
- フォロー体制が充実している業者を選ぶ
- 実績のある業者を選ぶ
自社の物流にマッチしている業者を選ぶ
業者を選定する際は、まず自社の商材や業界特性に適した業者かどうかの見極めが必要です。たとえば、アパレルなら検品や流通加工、医薬品なら温度管理やトレーサビリティ、食品なら賞味期限管理といったように、業界によって求められる物流機能は異なります。
また、自社の扱う商品特性(壊れやすい・重い・サイズが大きいなど)を踏まえて、適切な保管方法や配送ネットワークを持つかどうかも確認が必要です。これらが業者の標準オペレーションと合致していないと、業務の属人化やトラブルの原因になるため注意しましょう。
見積もり金額が妥当な業者を選ぶ
アウトソーシングのコストは、月額固定制、従量制、混合型など多様な体系があります。そのため、単に価格が安い業者を選ぶのではなく、「費用の内訳が明確で、サービス内容に見合った価格かどうか」を見極めることが重要です。
見積もりを比較する際は、以下のような要素に着目しましょう。
- 初期費用の有無
- 保管料・出荷手数料・返品処理費などの単価
- 梱包資材費やラベル発行費の設定
- 繁忙期の追加料金ルール
また、必要に応じて複数の業者から相見積もりを取り、費用対効果を比較検討することが推奨されます。サービス内容が似ていても、業者ごとに料金や条件が異なるため、細かな違いを理解して選びましょう。
フォロー体制が充実している業者を選ぶ
物流業務を外部に任せるからこそ、トラブル発生時の対応力やコミュニケーションの質が重要です。とくに初期導入時や繁忙期には、想定外のイレギュラーが発生する可能性があるため、業者のフォロー体制はしっかりと確認しておきましょう。
さらに、担当者が物流の専門知識を持っており、改善提案や運用アドバイスを積極的に行ってくれるかどうかも評価すべきポイントです。ただ作業を代行するだけでなく、パートナーとして業務改善を共に進めていける業者を選ぶことで、長期的な信頼関係が築けるでしょう。
実績のある業者を選ぶ
業者の信頼性を測るうえで、どのような実績を持っているかは重要なポイントです。「同業他社での導入実績があるか」「物流業界での運用歴は長いか」「どのような業種に強いか」などを事前に確認しておきましょう。
また、ISO9001やISO14001などの国際的な認証を取得している業者は、品質・環境管理に対して一定の基準を満たしていると判断できます。加えて、倉庫の立地条件、対応可能エリア、使用しているWMS(倉庫管理システム)なども確認しておきましょう。
物流アウトソーシングを導入する流れ
物流アウトソーシングの導入は、以下のような流れで進めます。
- 自社の物流に関する課題を洗い出す
- アウトソーシング先の業者を選定する
- 契約を締結する
- 物流業務を委託する
- アウトソーシングした効果を評価する
それぞれの手順をチェックしておきましょう。
自社の物流に関する課題を洗い出す
まず行うべきは、自社が抱える物流上の課題の可視化です。よくある課題には、出荷遅延の頻発・人手不足・在庫過多や欠品・物流コストの高止まりなどが挙げられます。これらを明確にすることで、「なぜアウトソーシングが必要なのか」という目的を具体的に設定可能です。
業務フローを図にまとめたり、工数を一覧化したりすると、委託すべき範囲や改善すべき箇所が明確になります。このフェーズで曖昧なまま進めてしまうと、業者選定や運用開始後のミスマッチが発生するリスクが高まるため注意してください。
アウトソーシング先の業者を選定する
課題と委託範囲が整理できたら、それに対応できる業者をリストアップし、比較検討を行います。費用・対応可能業務・得意分野・システム連携の可否・物流拠点の立地・業務実績などを複数の角度から評価し、自社と相性の良いパートナーを見つけることが重要です。
可能であれば現場見学やテスト運用を通じて、実際の運用イメージを確認することも推奨されます。
契約を締結する
業者が決まったら、委託内容や料金体系を明記した契約書を締結します。この際、委託範囲・納期・KPI・責任の所在・情報の扱い・トラブル時の対応方法などを細かく定めておくことで、後のトラブルを防ぐことが可能です。
また、運用開始日や移行スケジュールについても詳細に取り決めておく必要があります。必要に応じてテスト稼働や段階的な移行を取り入れることで、本稼働時の混乱を防げるでしょう。
物流業務を委託する
契約後、実際に物流業務の引き継ぎを行います。商品データの移行・在庫の移動・業務マニュアルの共有・システム連携の調整・担当者同士の引き継ぎなど、多くの作業が発生するフェーズです。
初期段階では、出荷ミスや納期遅延といったトラブルが発生しやすいため、日次での進捗確認や緊急対応フローの整備が欠かせません。スムーズな立ち上げには、密な連携と柔軟な調整が求められます。
アウトソーシングした効果を評価する
稼働開始から一定期間が経過したら、物流アウトソーシングの効果検証を行いましょう。たとえば、誤出荷率や納期遵守率、在庫精度、クレーム件数、コスト削減効果など、定量的な指標をもとに評価します。
問題が見つかれば業者と協議し、改善策を講じていくことで、より高品質な物流体制へと進化させることが可能です。また、KPIの見直しや新たな業務の委託範囲拡張なども、定期的に検討するのが望ましいでしょう。
まとめ
本記事では、物流アウトソーシングのメリット・デメリットや導入手順などについて解説しました。物流業務を専門業者に外部委託すれば、コスト削減・業務効率改善などのメリットが得られます。一方、トラブル時の責任の所在が不明確になるなどのデメリットもあるため、委託時には綿密なすり合わせが必要です。
物流アウトソーシング導入後の輸送中のトラブルに備えるなら、輸送中の環境を記録するデータロガーが役立ちます。輸送環境で用いるデータロガーには、株式会社藤田電機製作所の「WATCH LOGGER」がおすすめです。
WATCH LOGGERには、輸送中の衝撃・温度・湿度を記録できるモデルがあり、商品を破損させた外的要因を計測・記録できます。これにより、輸送中のどこで商品が破損したのかが把握でき、適切な対策を講じることが可能です。
現在、WATCH LOGGERのお試し無料レンタルサービスを実施中です。気になる方は、ぜひお気軽に当社にお問い合せください。